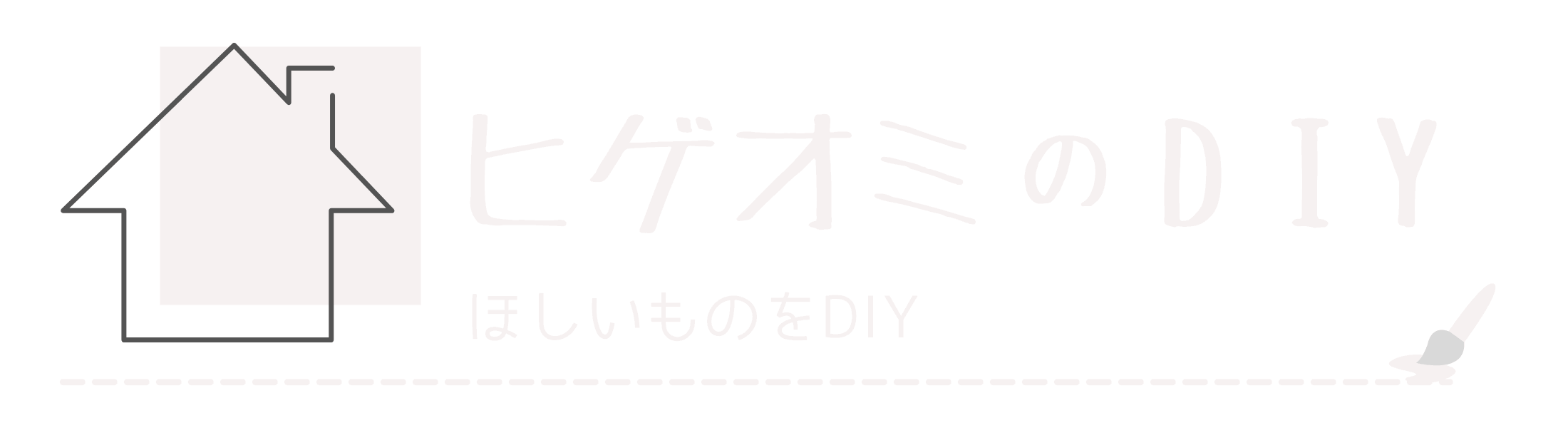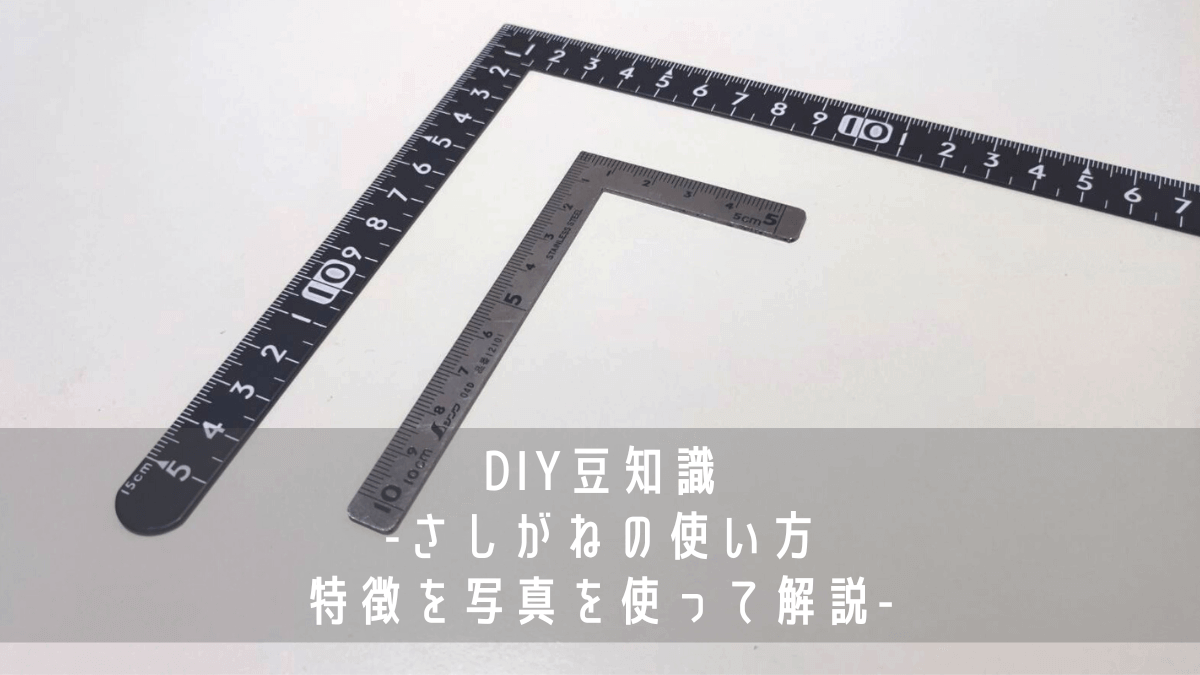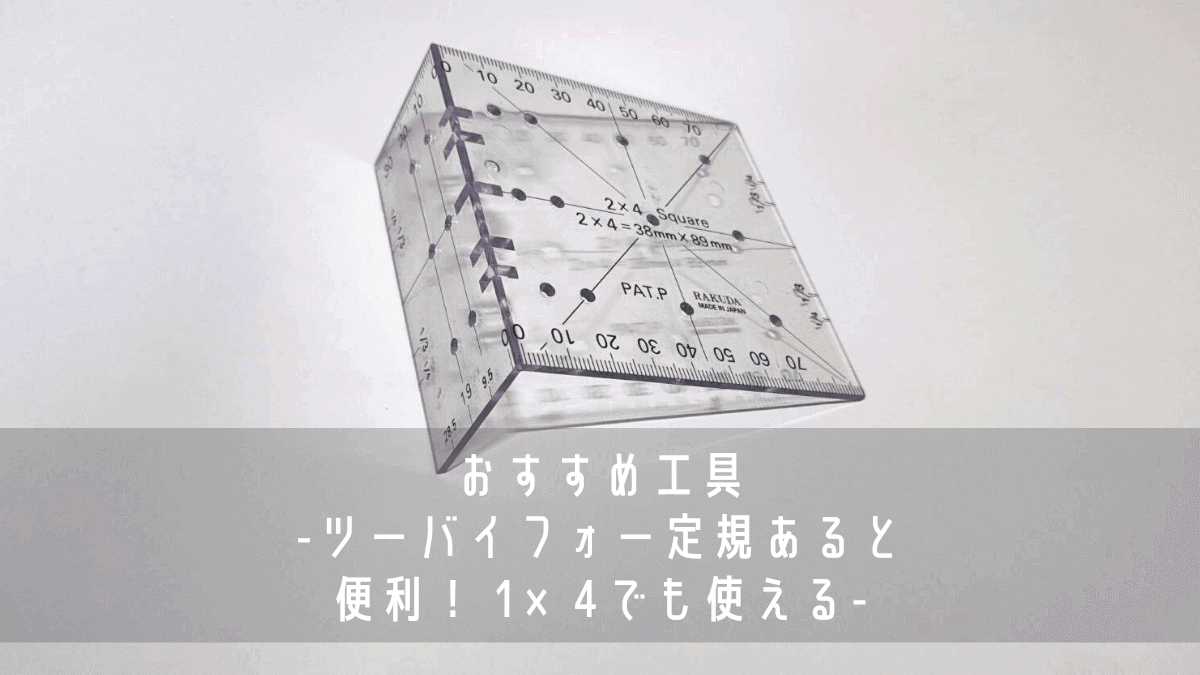直角に線を引いたり、長さを測ったり、勾配を出したりと便利な工具『さしがね』をご存じでしょうか?
DIY初心者だと、「さしがね」は知らないかもしれません。
「さしがね」を正しく使えば、効率よく作業でき製作物の精度が向上します。
私が普段から使用している「さしがね」の写真を使って詳しく紹介します。
「さしがね」の使い方で悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
それでは解説します。
「さしがね」とは
まず、「さしがね」は金属製でL字型をしてます。
長手と短手の表面・裏面に目盛りが付いてます。(特徴は内側にも目盛りがある)
他の呼び方としては、曲尺(かねじゃく)などとも呼ばれます。
「さしがね」の使い方
直角に線を引く


長手・短手どちらかを材料に引っ掛け、ペンで線を引きます。

しっかり押さえないとズレやすいです!
直角を確かめる


写真のように、直角を測りたい材料をさしがねのコーナー部分に当てます。
すきまがなければ直角です。
等分割する

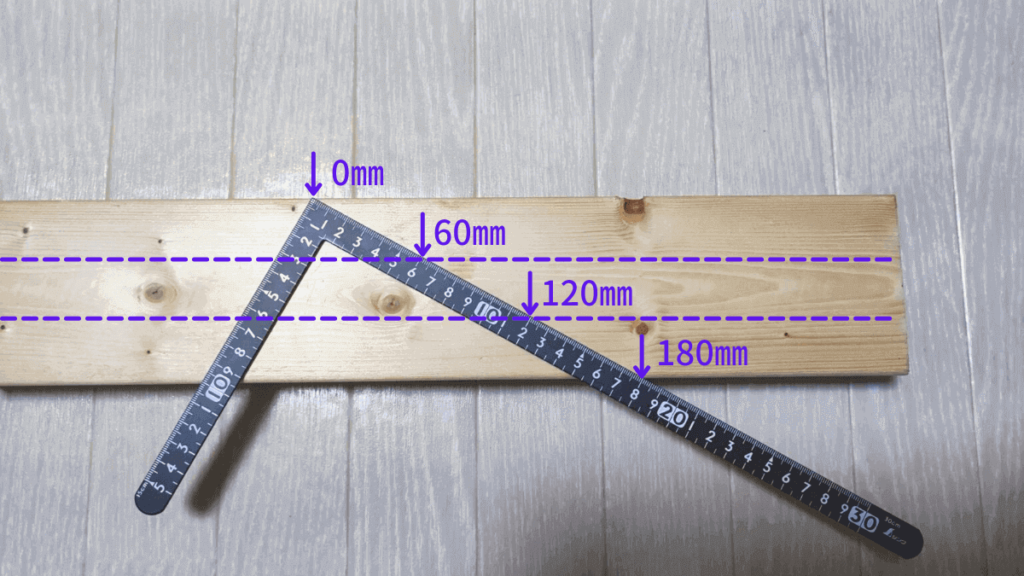
「さしがね」を使えば、木材のサイズを測らずに均等に分割できます。使い方は、「さしがね」の長手で材料の一辺に0を、もう一辺に等分したい数で割り切れる数字を合わせます。
例えば、3等分したい場合は3で割り切れる数字(60,120,180)の位置に印を付けます。
同じように2か所以上で印を付け線を引けば等分割できます。

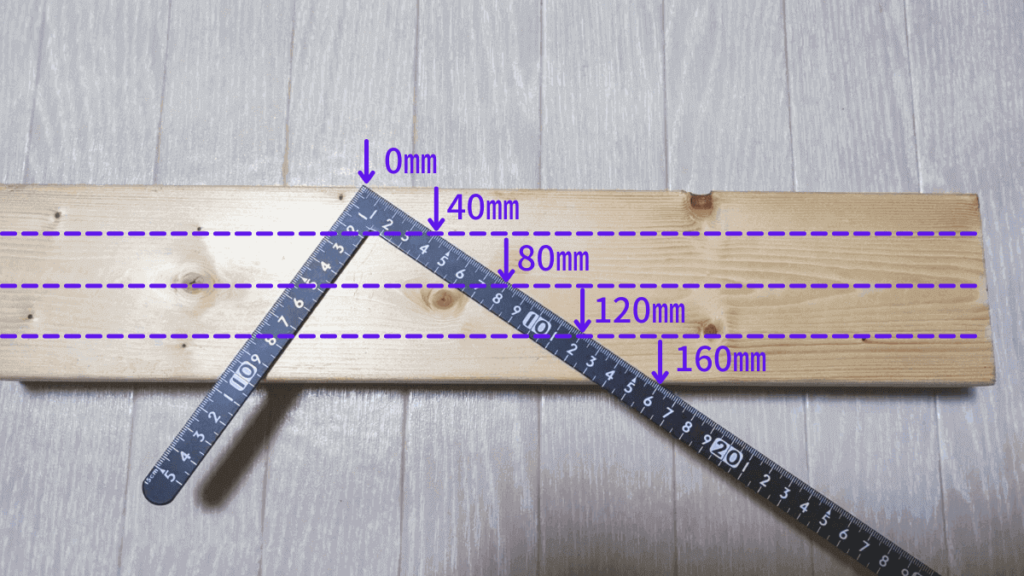
写真は4等分の場合です。
先程と同じように4で割り切れる数字(40,80,120,160)の位置に印を付けます。

慣れれば計算するより早いです。
角度を測る
45°の場合

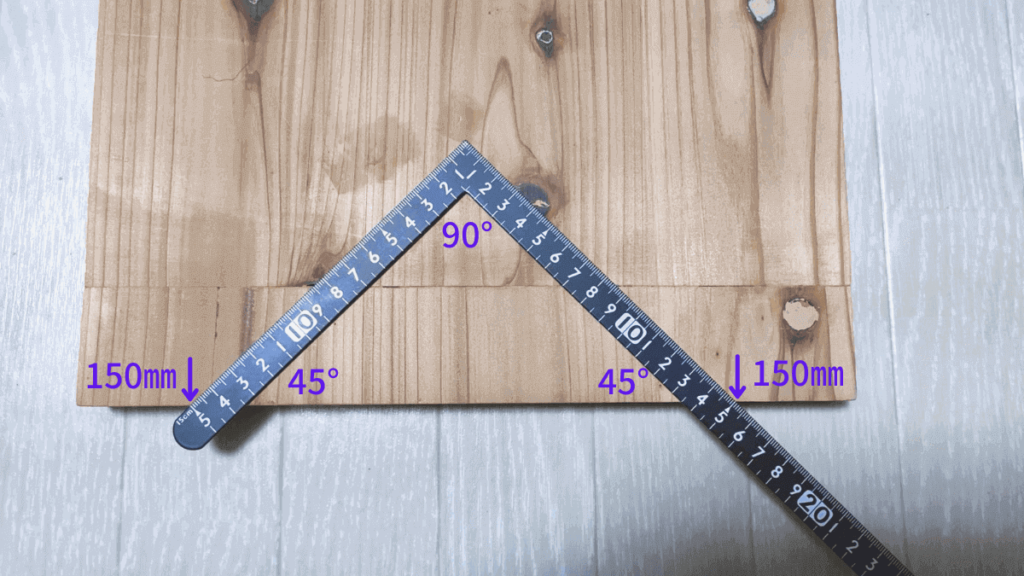
長手・短手を同じ長さに合わせると二等辺三角形になるので45°ができます。
写真は、両辺150㎜にさしがねを合わせます。
30°・60°の場合

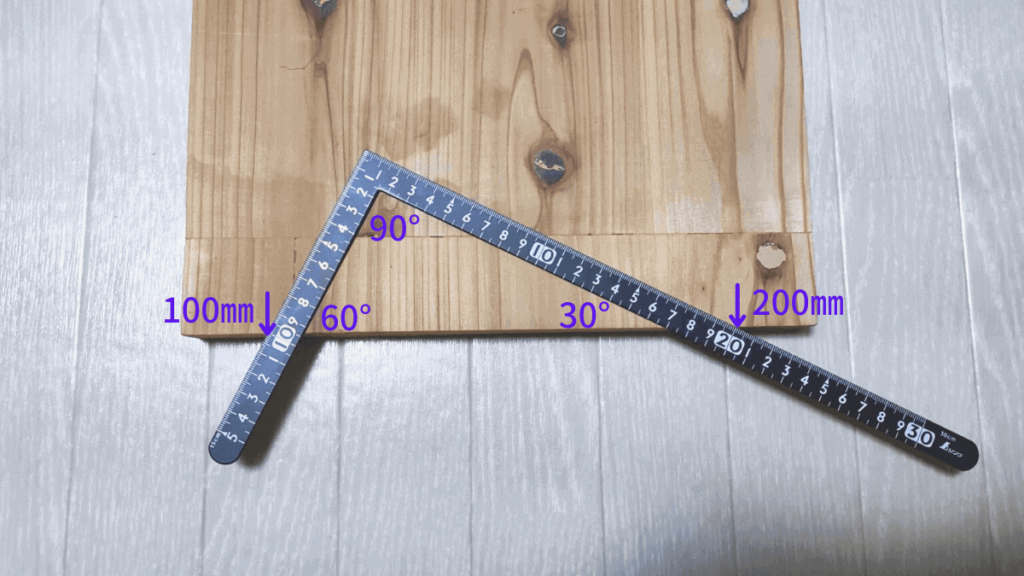
長手・短手を2:1の比に合わせると直角三角形になるので30°・60°ができます。
写真は、100㎜と200㎜にさしがねを合わせます。
角目・丸目の使い方
DIYで使うことはほとんどないと思いますが、「さしがね」の裏面に角目・丸目と呼ばれる目盛りのあるタイプがあります。
念のため、言葉の意味だけ紹介します。
角目とは?
角目で丸材の直径を測れば、丸材からとれる最大の角材寸法(正方形)が分かります。
角目の数字を通常の目盛りに変換して使ってください。
丸目とは?
丸目で丸材の直径を測れば、丸材の円周が分かります。
なぜ丸目と呼ばれているのかは、通常の目盛りに3.14倍した目盛りだからです。

角目・丸目で寸法測ると間違えますので注意してください。
角目・丸目ってなんだろう?と思ったら丸材に使うものと覚えるといいかと思います。
「さしがね」の紹介

今回の投稿が、みなさんのDIYで参考になれば幸いです
他の測定商品の紹介